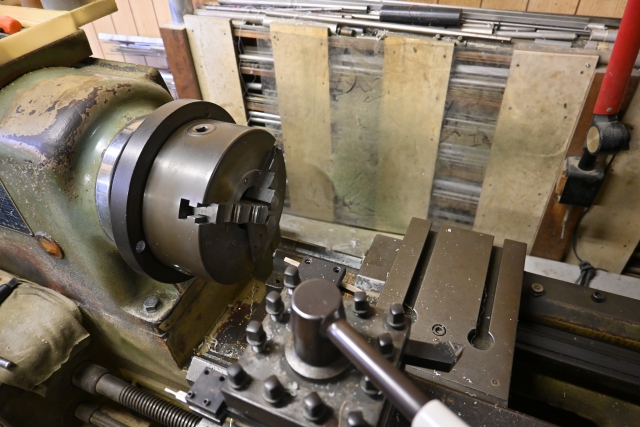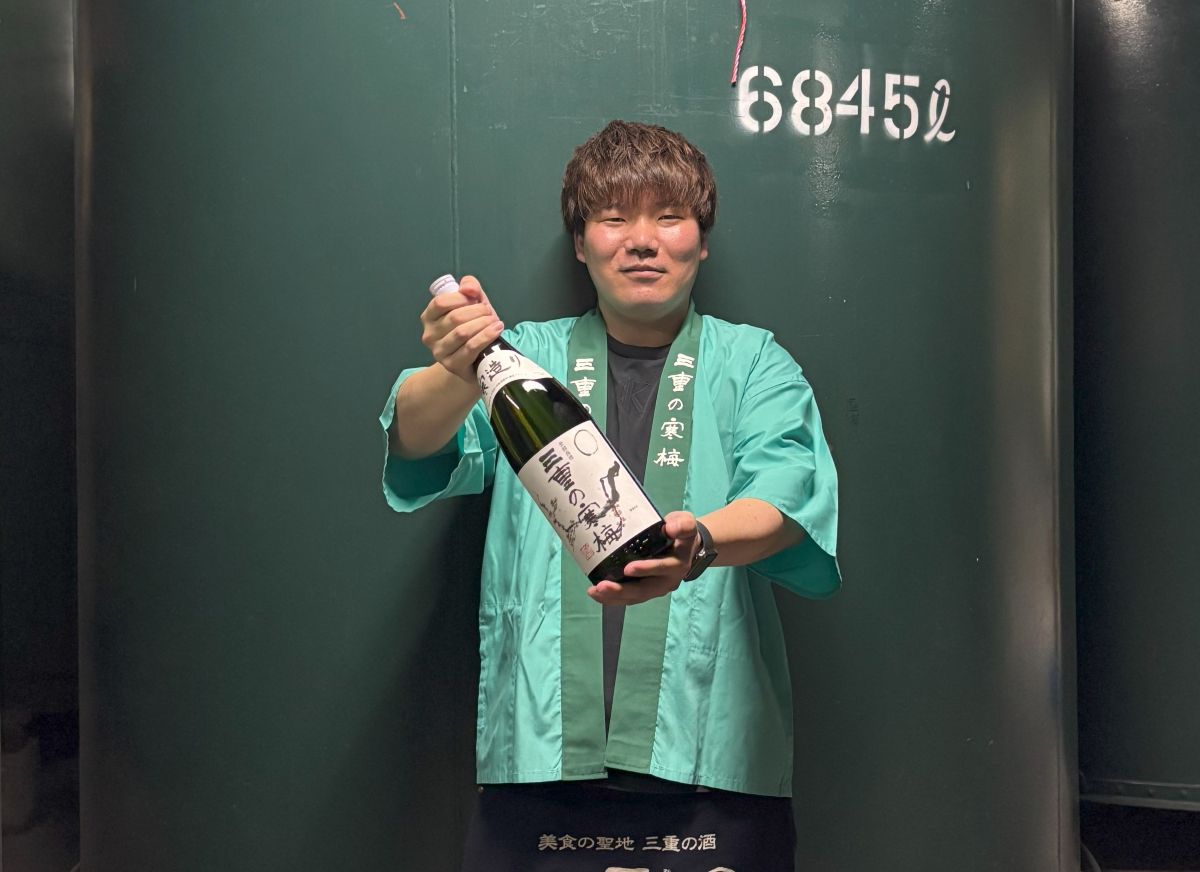鋼材や建材といった重量物から、電子機器やソーラーパネルといった精密機器まで、さまざまな貨物の運送を手がける運送会社。2015年に社長が就任して以来、本社移転や名古屋拠点の開設など、事業拡大を続けてきた同社だが、近年は燃料費の高騰や価格競争の激化などにより、収益性への課題が浮き彫りになっていた。
そこで、原価管理の精度を高め、見積もりシステムの改革に着手したことで、数字と向き合う姿勢が強まり、経営の可視化が進んだ結果、会社全体の意識にも変化が生まれました。
どのような相談をしましたか?

2015年の代表就任以降、本社の移転や名古屋拠点の開設など、会社は着実に成長と拡大を遂げてきました。組織体制も整いつつある中で、より安定した経営基盤を築くためにも、財務に関する知識を深め、資金繰りへの対応力を高めていきたいという想いが強くなっていきました。
これまでも税理士の先生には、一般的な経営指標をもとに数字の確認や助言をいただいていましたが、日々の業務に即したより実践的な視点や、経営判断に活かせる細かな分析については、さらに踏み込んだ管理が必要だと感じるようになりました。
そうした背景や金融機関からのすすめもあり、みえビズに相談することにしました。
どのような助言を受けましたか?

まずは「1台あたりの原価を正確に把握すること」の重要性を指摘されました。運送業界で一般的に使用されているソフトを活用していましたが、それは主に運行履歴を記録するためのもので、日々の経費入力や収支分析など、原価管理の活用には限界がありました。
そこで、より実務に即した管理を行うために、既存のソフトとは別に、自社独自の原価管理ツールを一から作成することにしました。
また、従来の「売上から利益を計算する」発想ではなく、「目標粗利から逆算して適正価格を見積もる」考え方への転換も促されました。特にスポット案件が多い当社にとって、国交省の標準運賃ではなく、実態に即した価格設定の必要性があると助言いただきました。
改善提案を受けて何をしましたか?

これまでの走行距離や燃料代、車両ごとの取得価格・残価、年間の維持費用といった数値を丁寧に集計・分析し、それらのデータをもとに計算式を設計。専門家と相談しながら時間をかけて自社用の原価計算ツールを作成し、トラックごとの実燃費や利益を正確に管理できる仕組みを整えました。
これにより、これまで過去の実績により算出していた見積もりも、目標利益から逆算して具体的な価格を提示できるようになり、日々の配送業務がどれだけ利益に直結しているかを数字で把握できるようになりました。
支援を受けてどのように変わりましたか?

これまで試算表ベースでしか見えなかった見積の粗利が、今回の取り組みによってかなり具体化し、「仕事を終えてから正確な利益がわかる」状態から、「見積段階である程度正確な粗利が把握できる」状態へと変化しました。数字を基に現状を捉え、未来を見据える姿勢が社内にも少しずつ浸透し始めています。
ツールの導入や仕組みづくりには苦労もありましたが、「社長としての責任」と「社員とともに育つ会社」の在り方を実感できた、大きな一歩となりました。今後も財務管理の精度をさらに高めながら、設備投資や新型車の導入などにも計画的に取り組んでいきたいと考えています。
行動計画
車両別の採算性の確認
管理会計の導入・改善- 原価計算ツールを用いて、トラック1台当りの日々の原価管理・粗利益の把握を行う
目標利益額の設定・管理
- 自社の目標利益額を定め、原価計算ツールを用いて日々の粗利益額の管理を行っていく